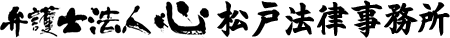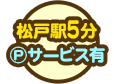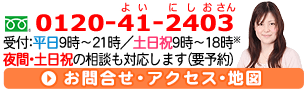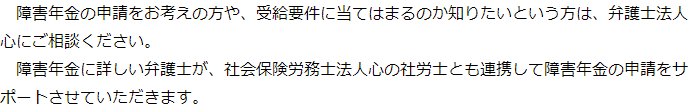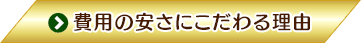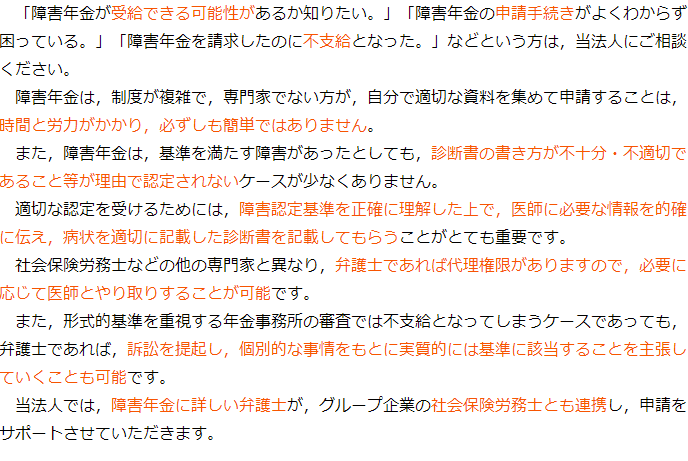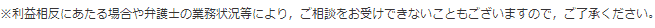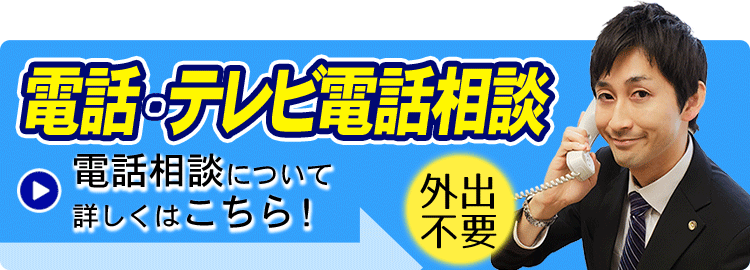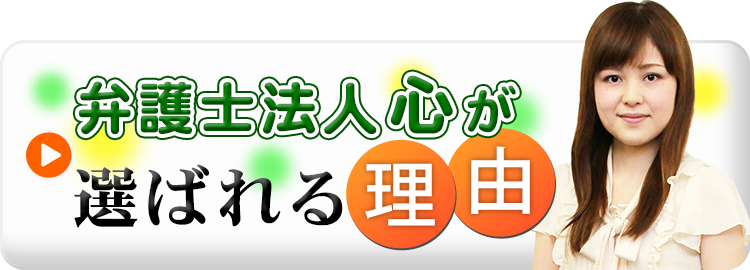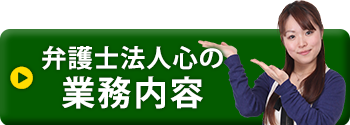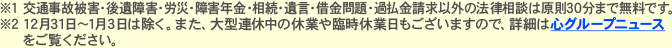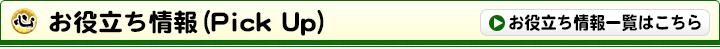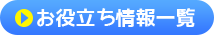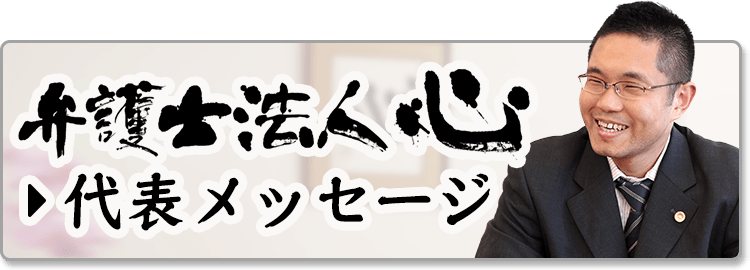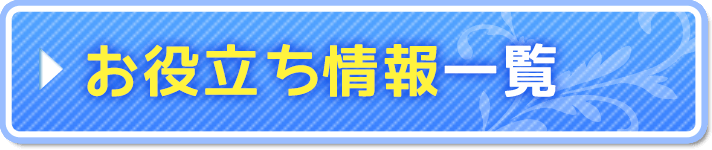障害年金
2種類の病気を発症した場合の障害年金
1 2種類の病気を発症した場合

2種類の病気を発症した場合でも、2倍の障害年金を受け取れるわけではありません。
1人1年金の原則がありますので、複数の障害年金の受給権が発生したとしても、もらえるのは1つの障害年金だけです。
しかし、これでは、複数の病気が重なることで障害の程度が重くなっている場合には、障害の状態に応じた障害年金を受け取ることができなくなります。
そこで、2つ以上の障害がある場合には、原則として2つ以上の傷病を併せた状態での障害等級を判断し、それに応じた障害年金を受給することになります。
2 併合(加重)認定
2種類の病気を発症して障害状態が発生した場合には、障害認定基準に基づき、原則として2つの病気を合わせた障害の状態で障害等級が判断されます。
これを、併合(加重)認定といいます。
原則として、併合認定は、①障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合、②「はじめて2級」による障害年金を支給すべき事由が生じた場合(併合認定)、 ③障害年金受給者(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る)に対し、さらに障害年金(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る)を支給すべき事由が生じたとき(加重認定)の3つに分かれています。
併合(加重)認定は、障害年金の併合等認定基準の併合判定参考表を参考に認定されており、併合して等級が上がる場合と併合しても等級が上がらない場合があります。
単独の傷害では障害年金を受給できないような方でも、発症した複数の障害が合わさることで受給できる場合もありますし、複数の傷病と併合しても等級が変わらず影響がないこともあります。
併合しても等級が上がらない場合には、受給金額が一番高いものだけを申請することもあります。
3 専門家への相談
複数の傷病を発症して障害年金の申請をする場合には、等級の判断が非常に複雑になり、どの傷病で申請をするのか等の判断が必要になることがあります。
2種類以上の傷病を発症して障害年金の申請を考えている方は、お早めに弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
障害年金が不支給になってしまった場合の対応方法
1 障害年金が不支給になってしまったら

障害年金の申請をしたものの、日本年金機構の審査の結果受給が認められなかった場合、その後どのように対処すればよいのか、その後の方針等についてご説明いたします。
2 不支給の理由を確認する
障害年金が不支給となったか否かは、日本年金機構から送られてくる不支給決定通知書を受け取ることで確認することになります。
不支給決定通知書には、不支給の理由も同封されていますので、一応はなぜ不支給という結果となったかを確認することができます。
「一応」というのは、申請傷病の種類にもよりますが、不支給の理由の記載はかなり簡素で、列挙されている理由からなぜ不支給という決定に至ったのかほとんど分からない場合も多いからです。
追加で不支給の理由を調査する必要がある場合には、認定調書等、審査の経過に関する情報についての情報開示手続きをすることが有効となる場合があります。
3 考えられる方針
⑴ 審査請求
不支給決定通知書が届いた後、想定される方針の1つは審査請求です。
これは、不支給という判断そのものについて再考を求める手続きです。
不支給の理由について、判断結果を覆すことができれば、申請した時点からの障害年金の受給が認められることになります。
注意として、不支給の結果を知った日の翌日から3か月以内に手続きをとる必要があるため、申請の期限に気を付けなければいけません。
情報開示も、開示されるまで時間がかかるため、審査請求の期限については十分注意が必要です。
審査請求の理由は後日追加提出することもできますので、とりあえず期限内に審査請求の申請をしておき、情報収集を進めるということも考えられます。
⑵ あらためて障害年金の申請を行う
もう1つは、あらためて障害年金の申請を行うという方針です。
認定日請求等、過去の申請の結果を争うとすれば審査請求を行うしかないと考えられますが、再度の申請の場合には、後日の症状悪化を理由として事後重症請求を行うことになると考えられます。
不支給の場合、基本的には各等級に該当する障害の状態にないという判断となっています。
不支給の理由次第ですが、例えば「診断書上検査の数値が基準を下回っている」というのが理由とされていた場合、遡って過去の検査数値を変えることはできませんが、現在の検査で基準を上回っているのであれば、前回の申請で不支給となった理由の1つは現在なくなっている、ということになりますので、再度の審査をする意味が出てきます。
なお、上記の方針はどちらかしかできない、というわけではありませんので、審査請求をしつつ、認められなかった場合に備えて再度の申請の準備を進めておく、といったことも考えられます。
4 却下決定について
なお、障害年金が受給できないという意味で結論は同じですが、障害年金が受給の前提要件を満たしていないと判断された場合には、不支給決定ではなく却下決定という結論が出ます。
この場合、例えば保険料の納付ができていなかった、ということであれば、過去に遡って納付要件を満たすことはできません。
一方、「初診日の特定ができていない」等の理由の場合、追加資料の提出などで決定を争うことができる場合があります。
不支給決定は障害の程度の問題、却下は審査の前提要件の問題で、それぞれ不支給という結果となっていることが分かります。
決定の内容によって争い方が変わってくる点にご注意ください。
働いている人も障害年金を受給できますか?
1 障害年金とは?

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金のことを言います。
2 働いていると障害年金は受給できないのか
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金であるという障害年金の性格からすると、働いている場合は障害年金を受給することはできないのではないかと思われるかもしれません。
しかし、働くことができる場合でも、必ずしも障害年金を受給することができないとは限りません。
3 問題なく働けていても障害年金の受給対象となる場合
障害年金の対象となる障害の内容及び程度は「障害認定基準」に定められています。
そして、この基準では、人工関節、心臓ペースメーカー、人工透析、人工肛門造設など、働いているか否かにかかわらず、障害年金の受給対象とされているものがあります。
そのため、このような障害の場合は、仮に働くことができていたとしても、障害年金を受け取ることができます。
4 働いていることが障害年金の受給に影響を及ぼす障害
上記のような障害に対して、精神系や内科系の疾患の場合は、障害が原因で日常生活や仕事にどのような影響が生じているのかを確認されることになりますので、働くことができていることは障害年金の受給の可否に影響を及ぼします。
もっとも、精神系や内科系の疾患の場合でも、働いていたら障害年金が即不支給になるというわけではありません。
障害のせいで遅刻・早退・欠勤が非常に多くなってしまっていたり、職場から就労時間や就労条件について特別な配慮を受けていたりする場合は、障害年金の受給対象となる場合もあります。
そのため、働いてはいるが、精神系や内科系の疾患で障害年金を受給したいという方は、就労の状況や職場から受けている特別な配慮の内容、就労後の心身の状況等について、十分に医師に伝えていただき、診断書に反映してもらうことが非常に重要です。